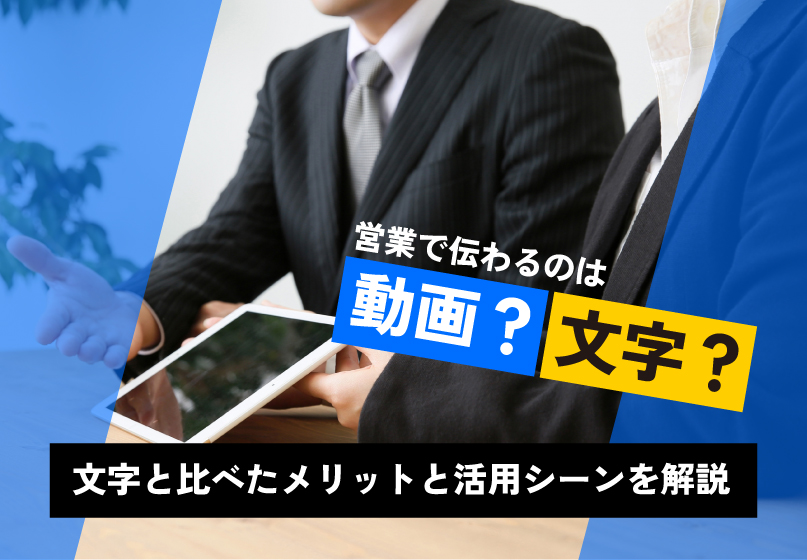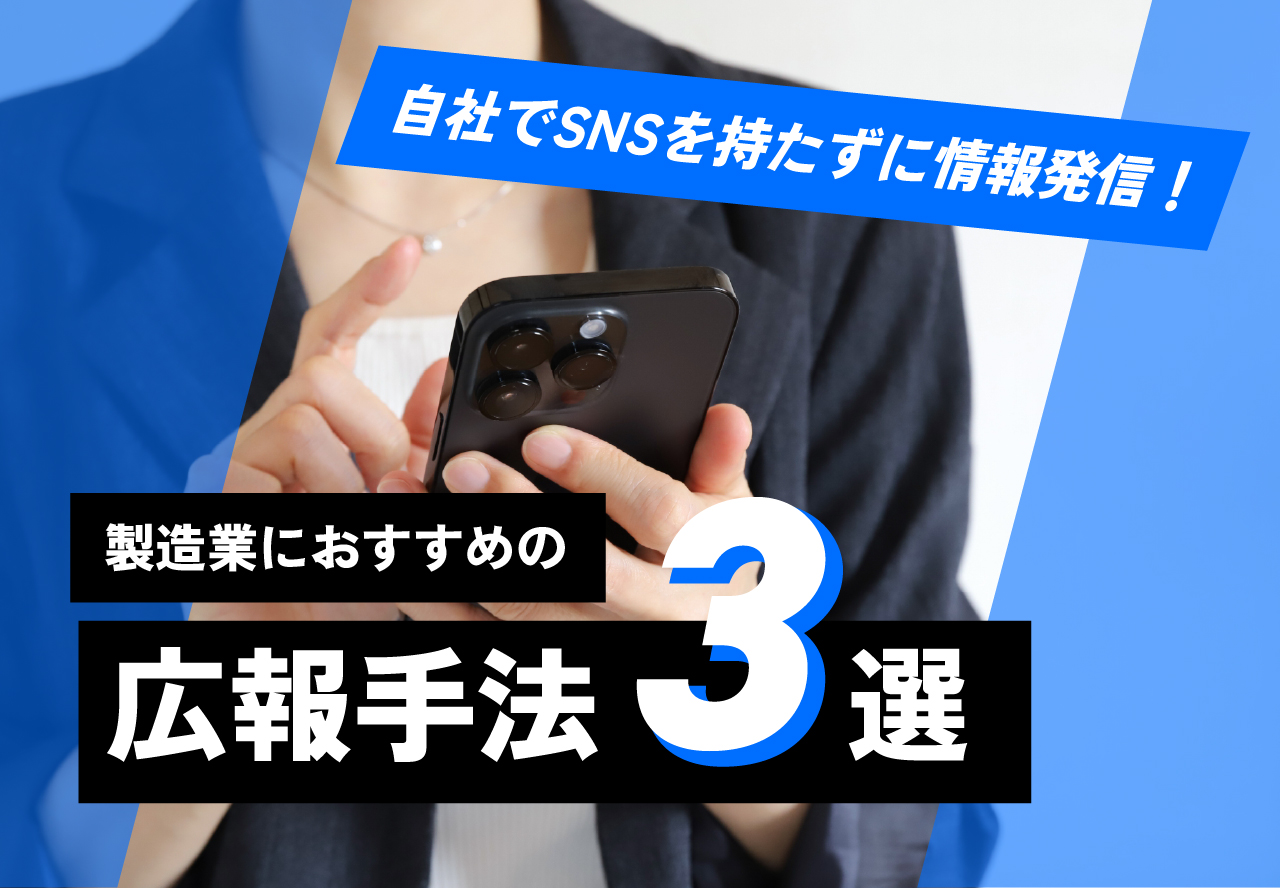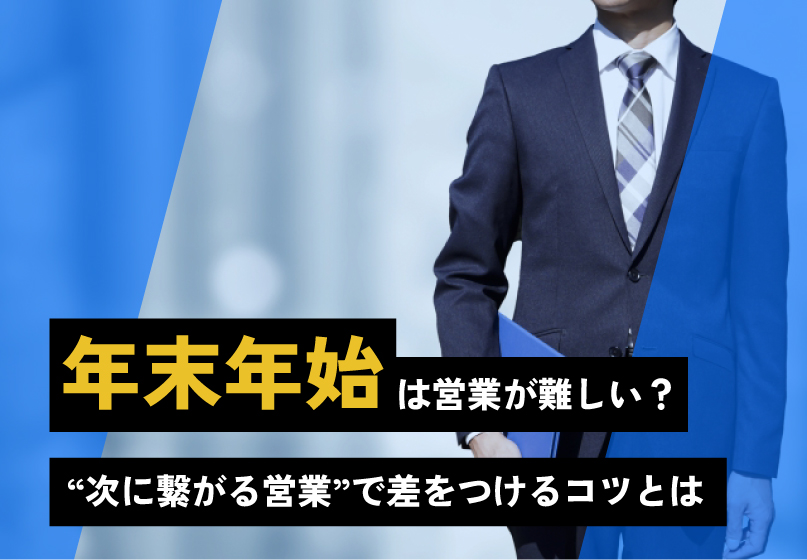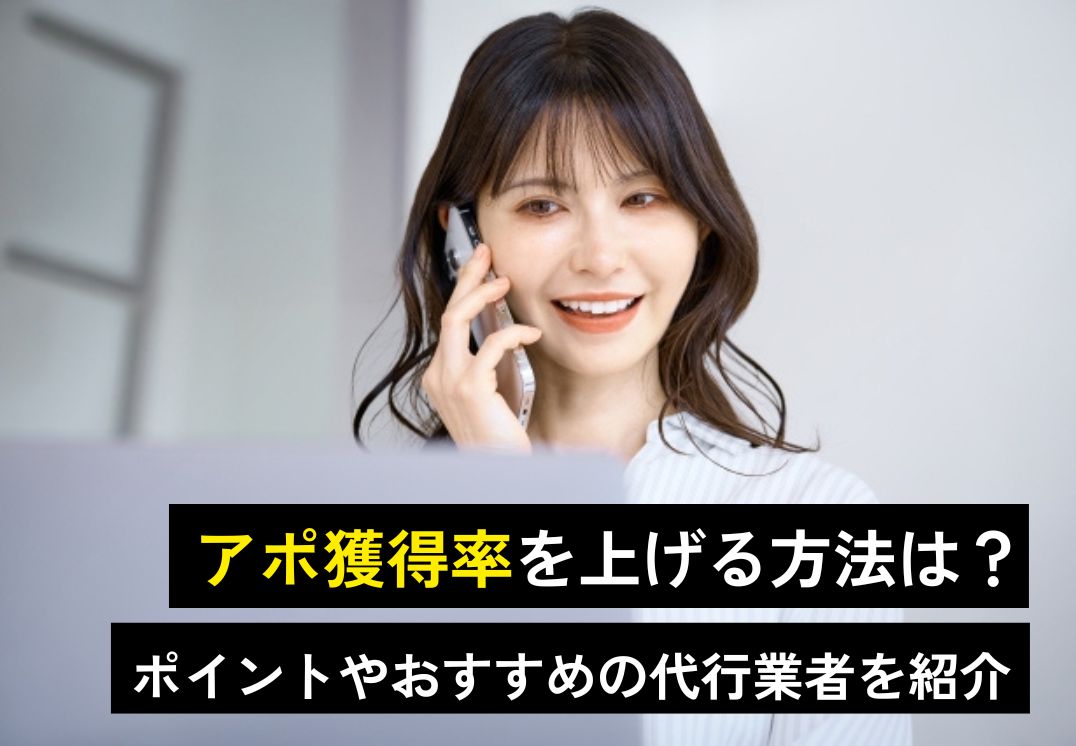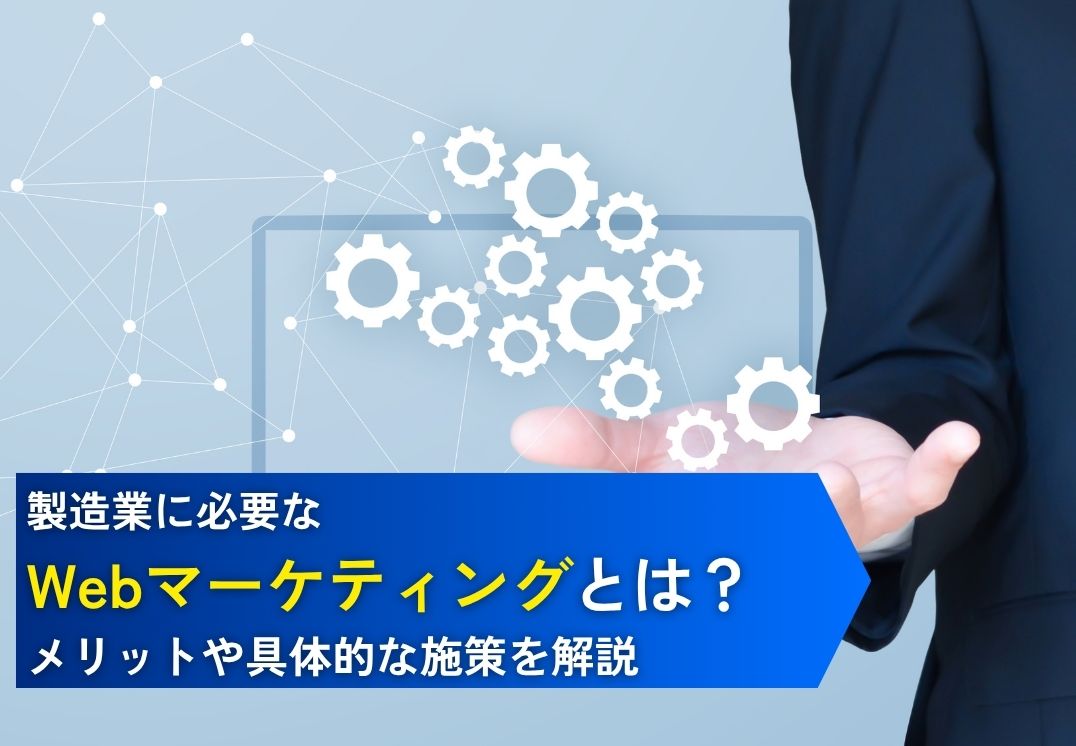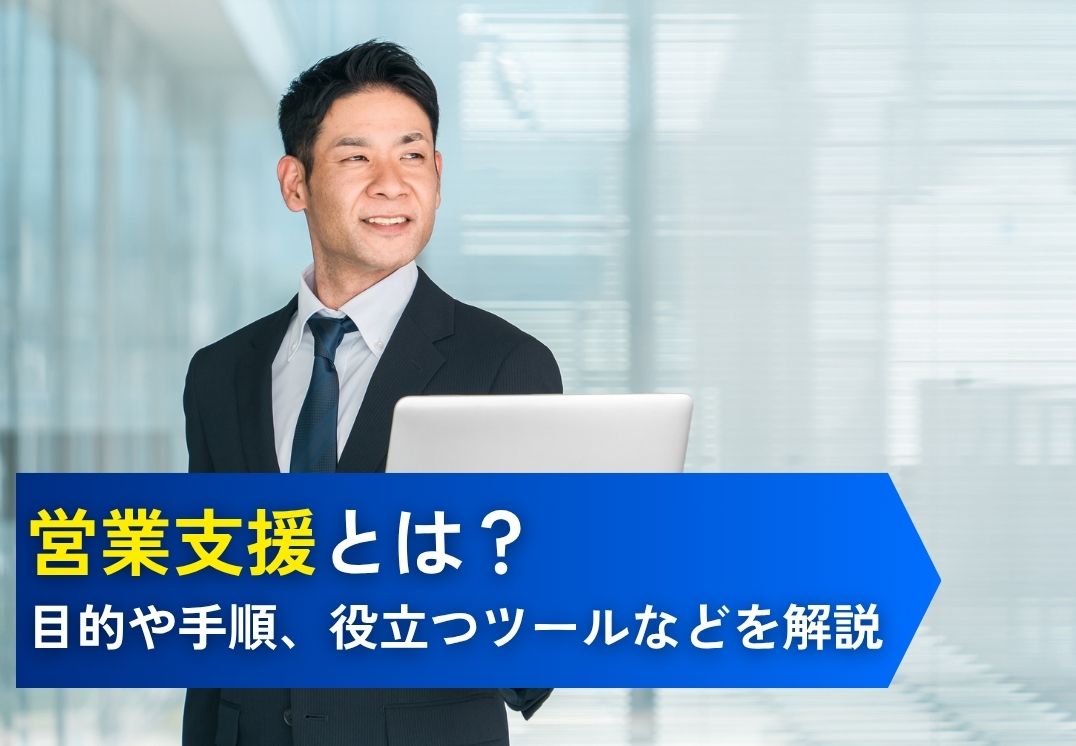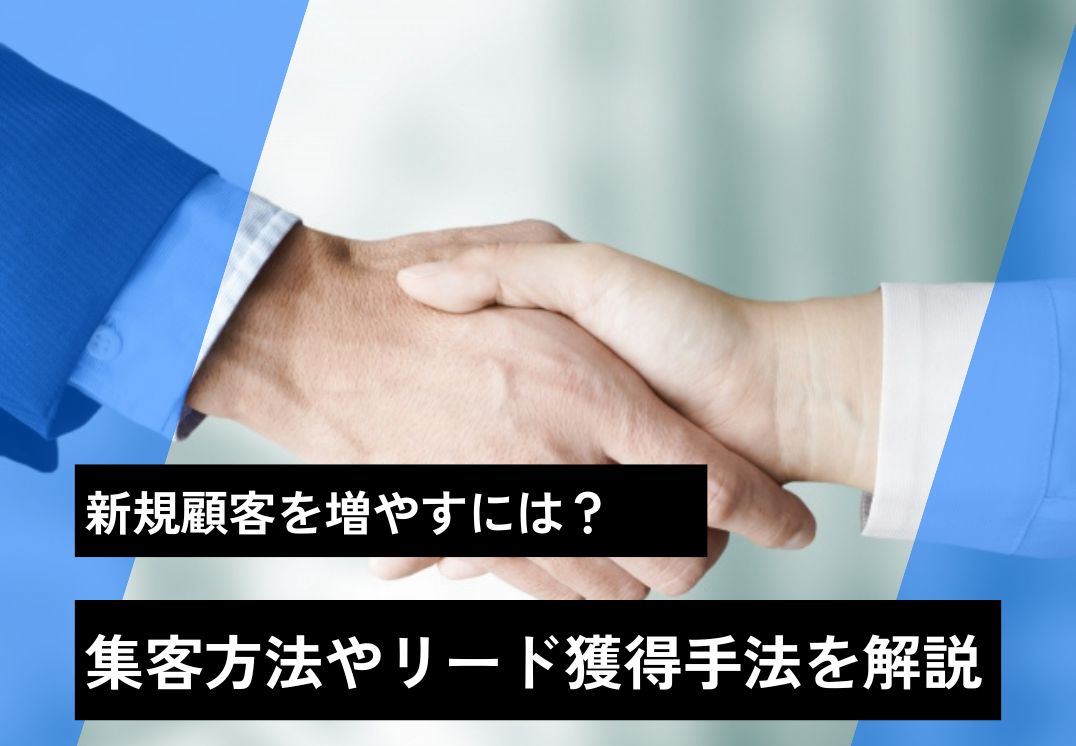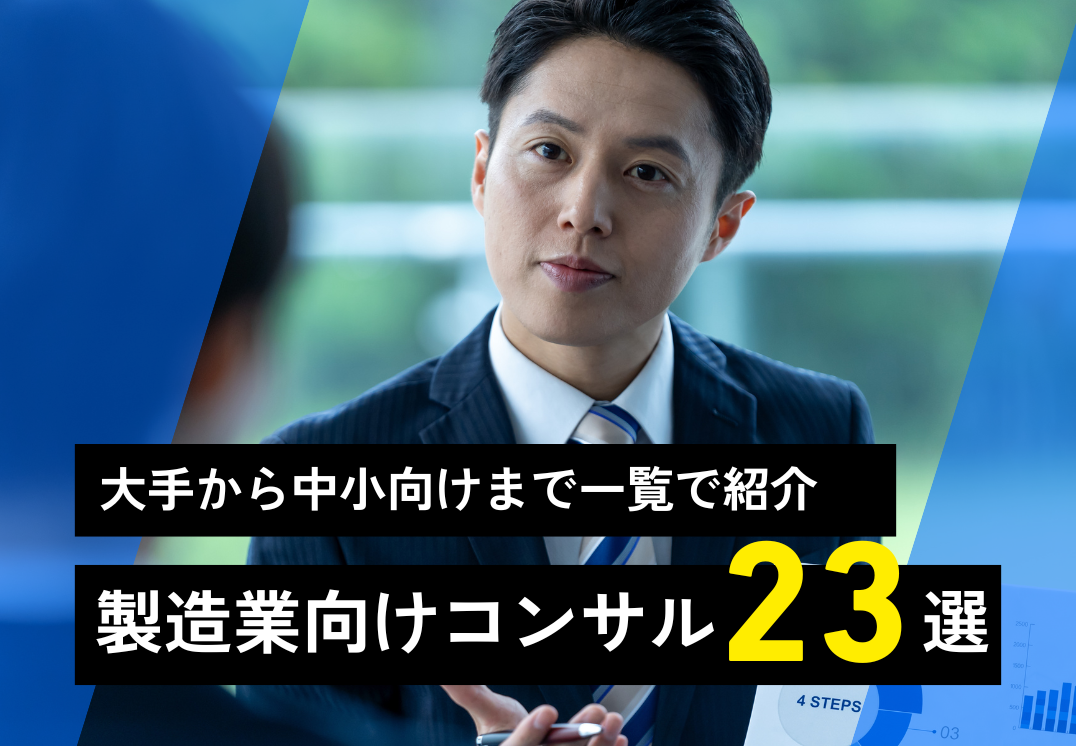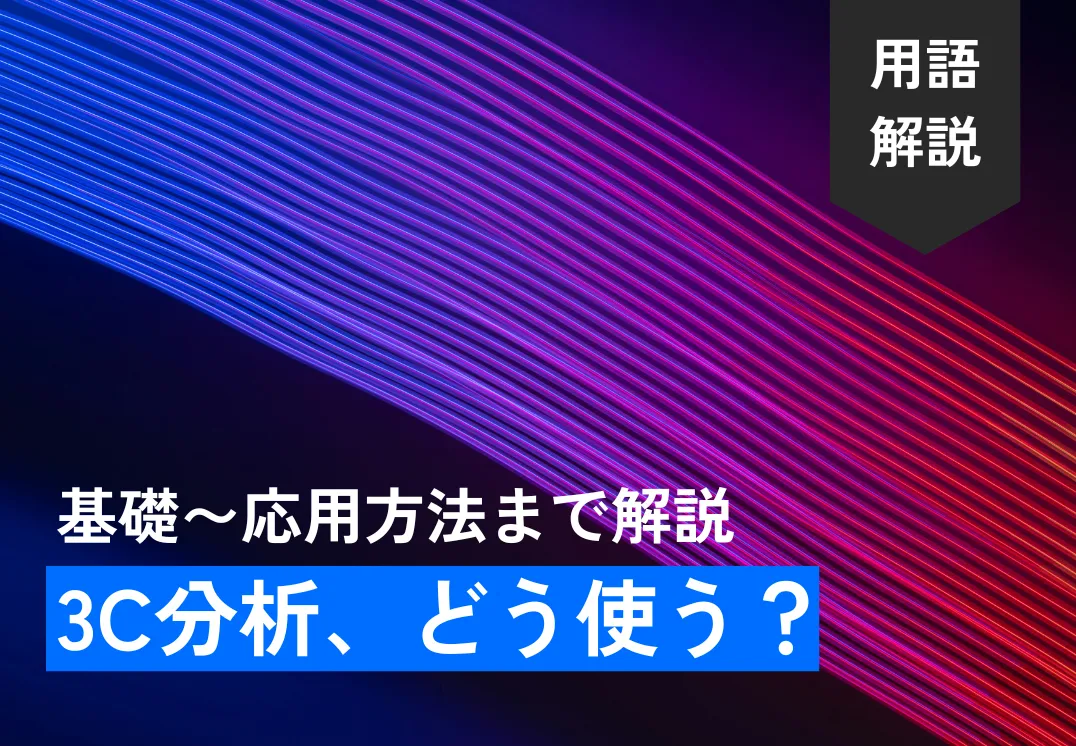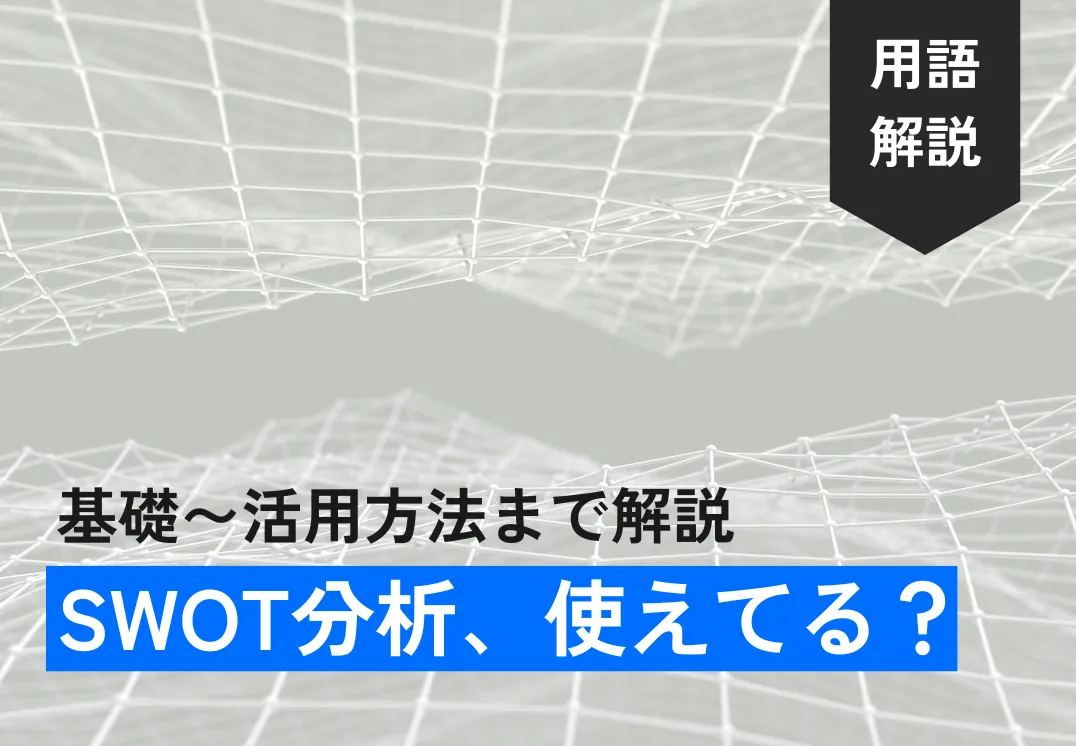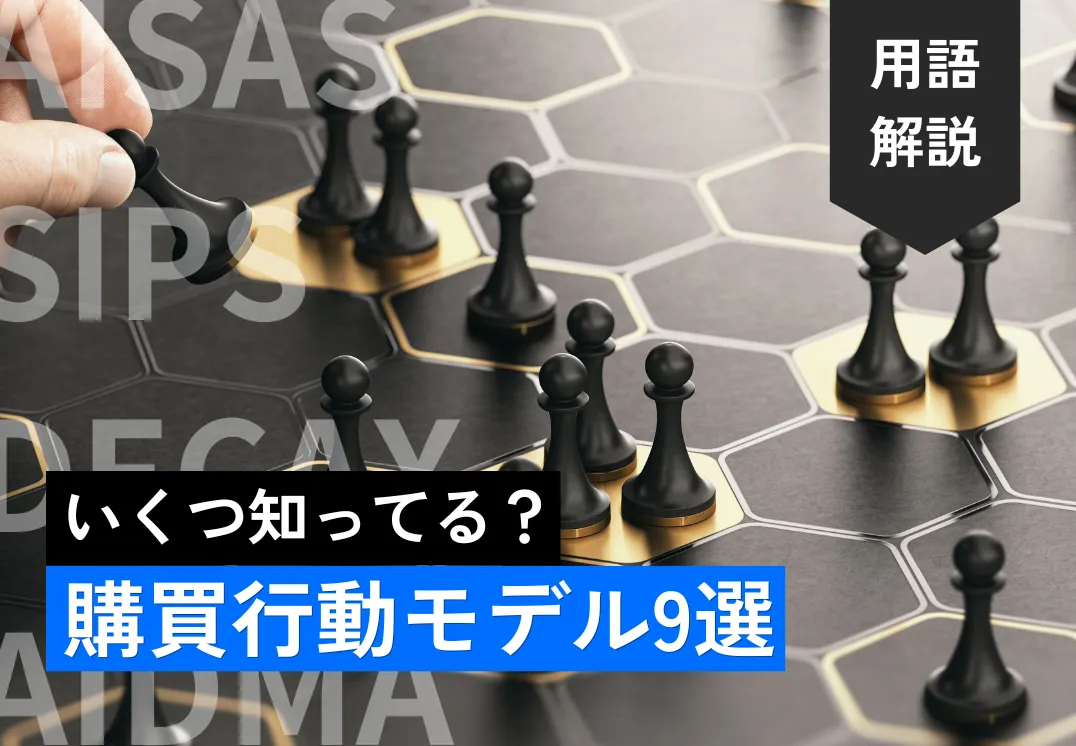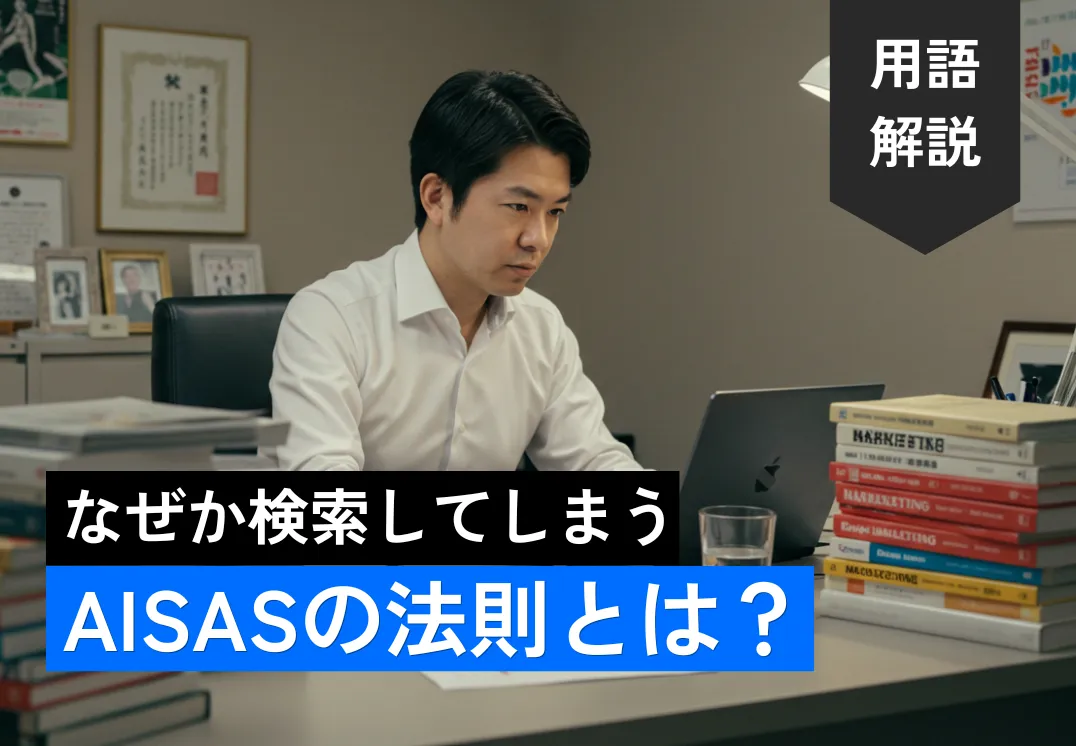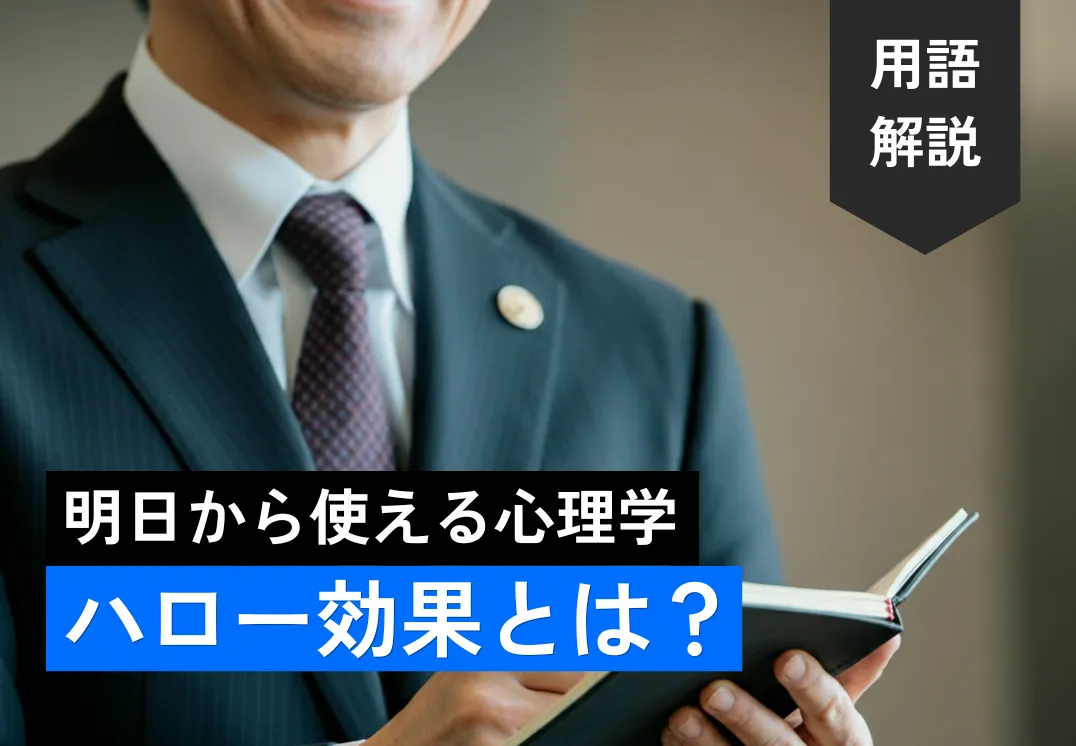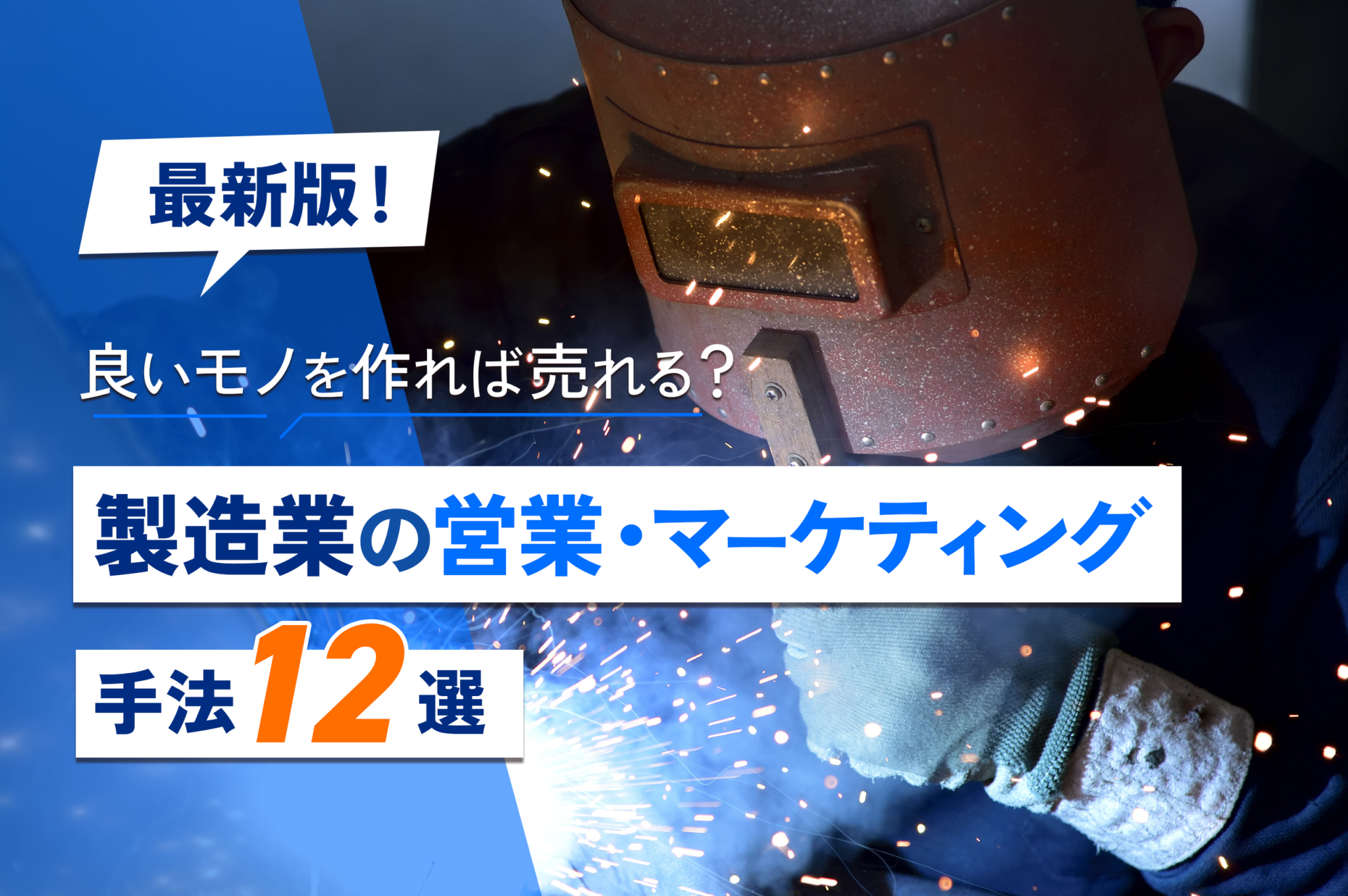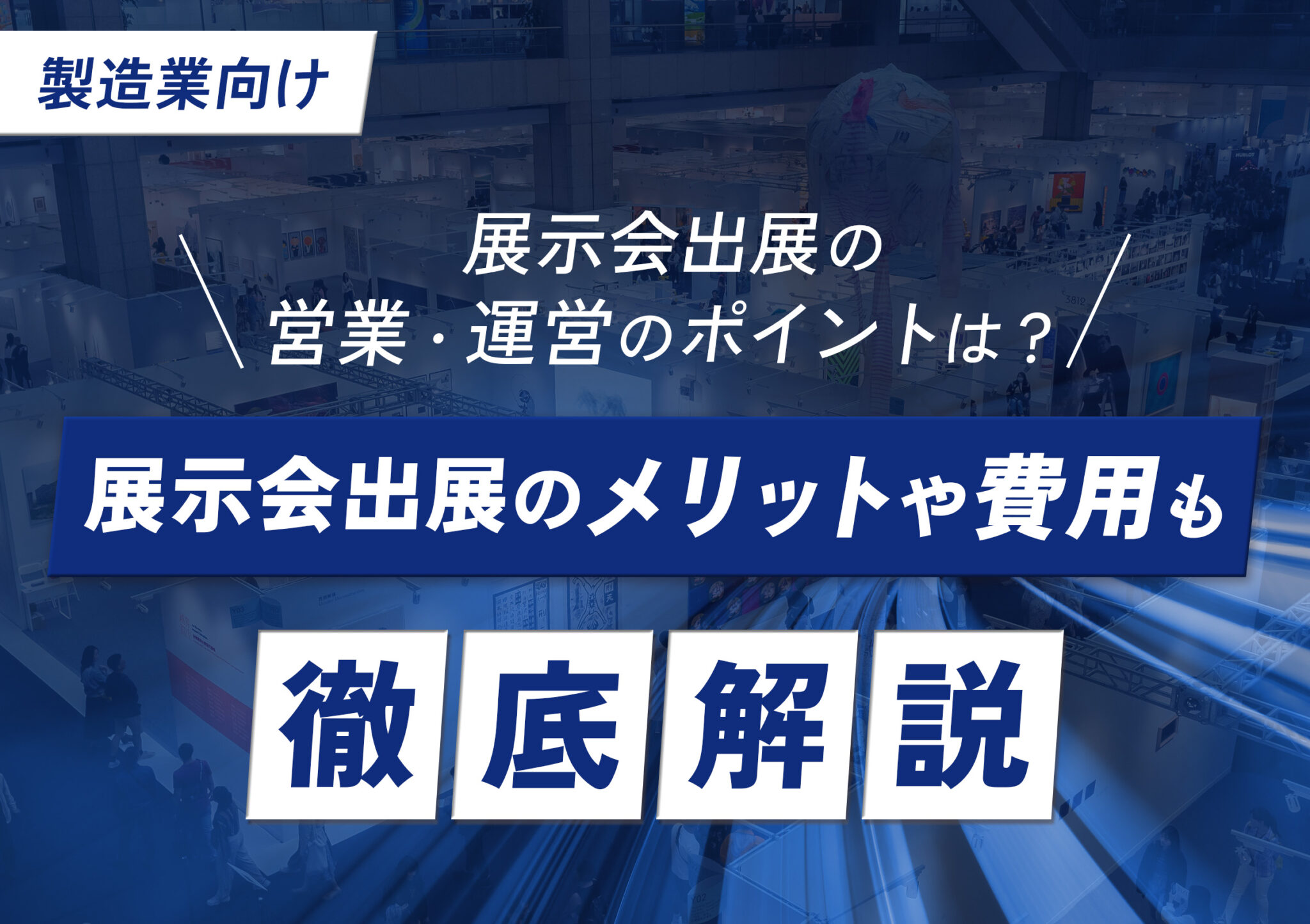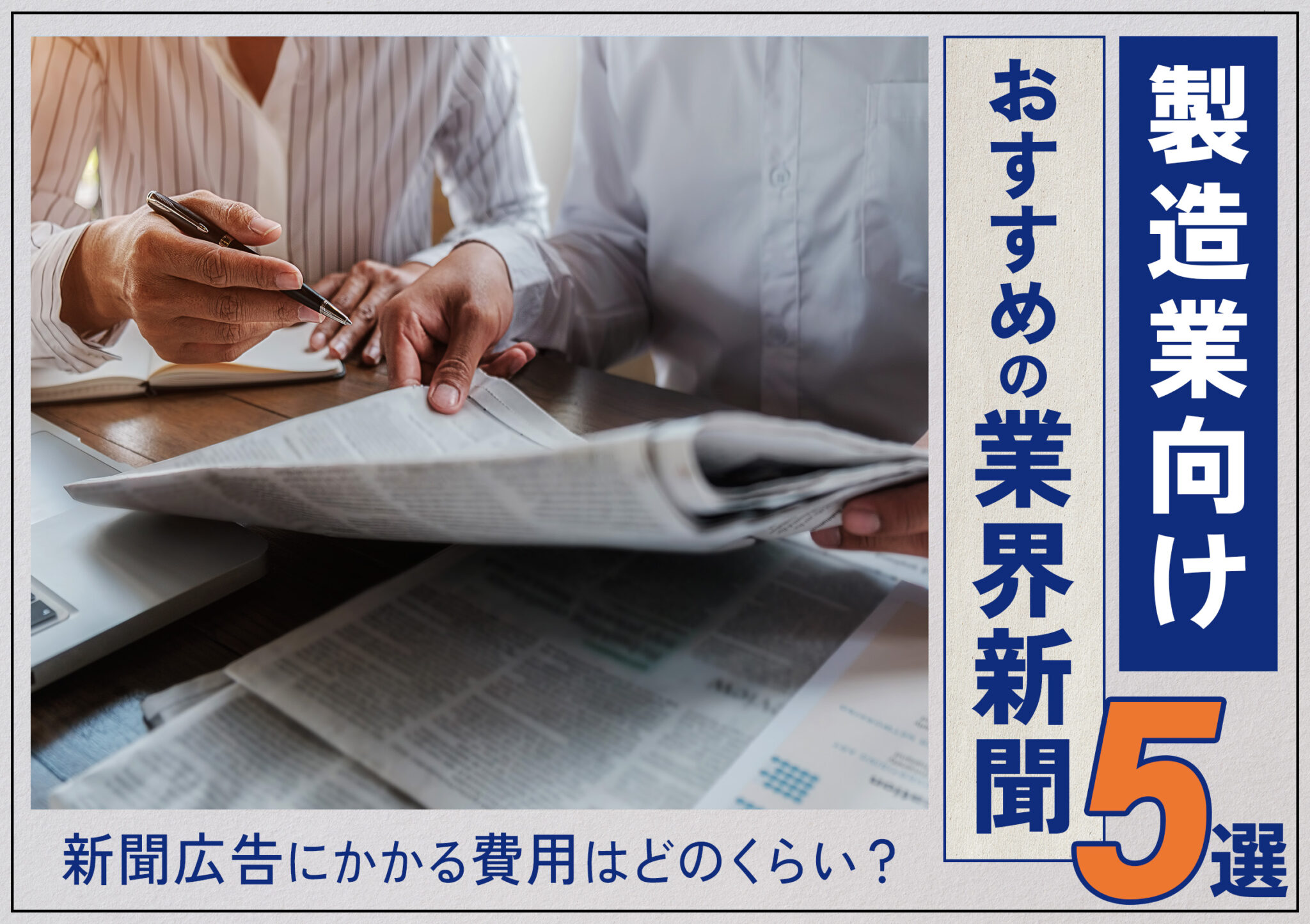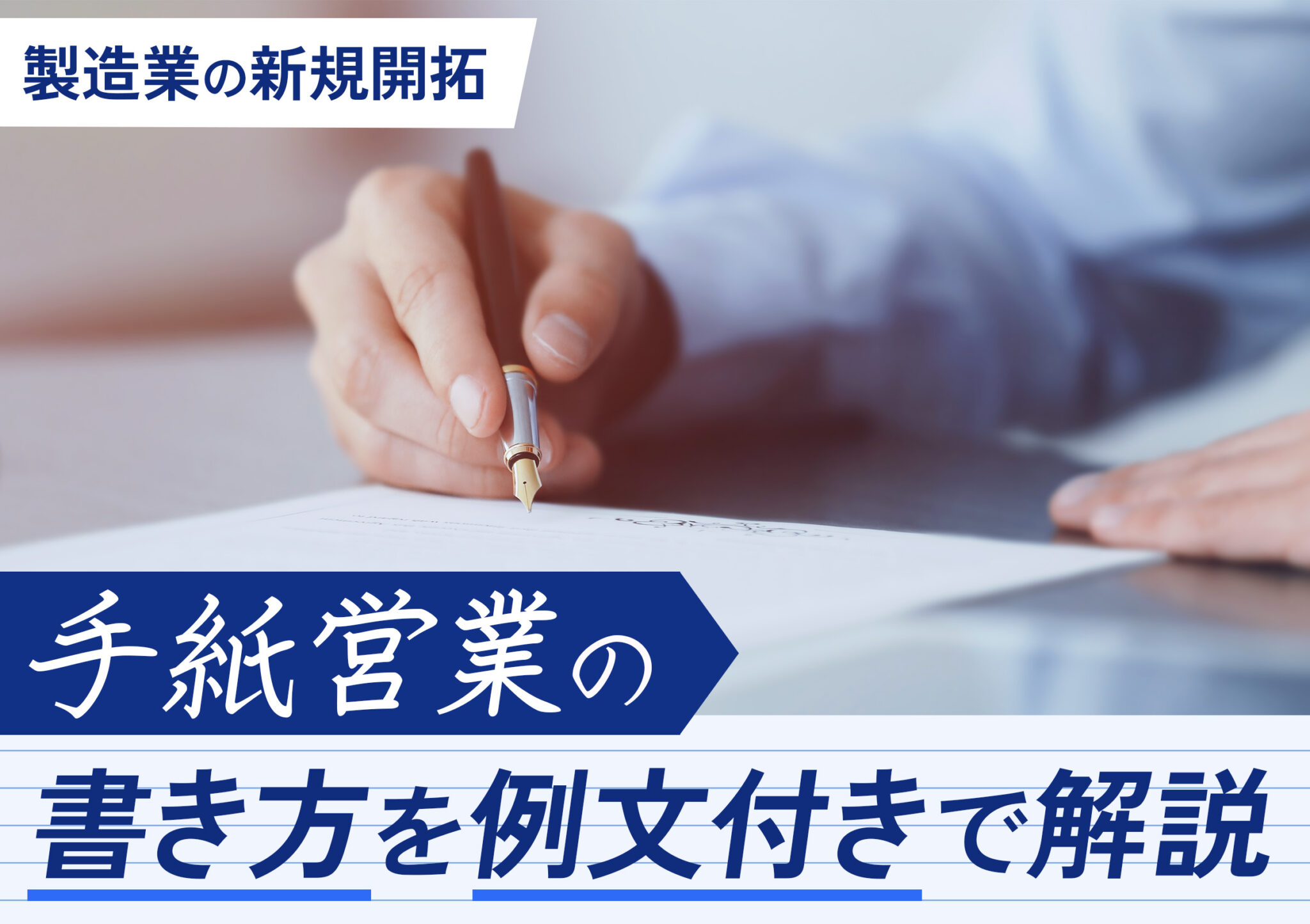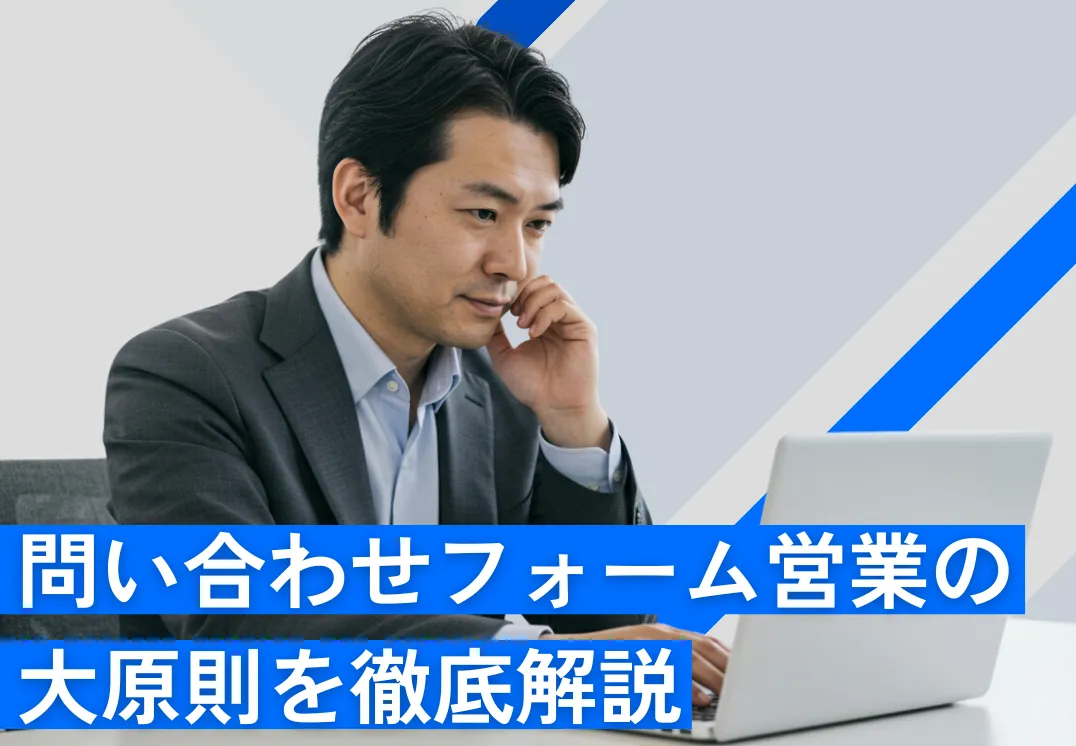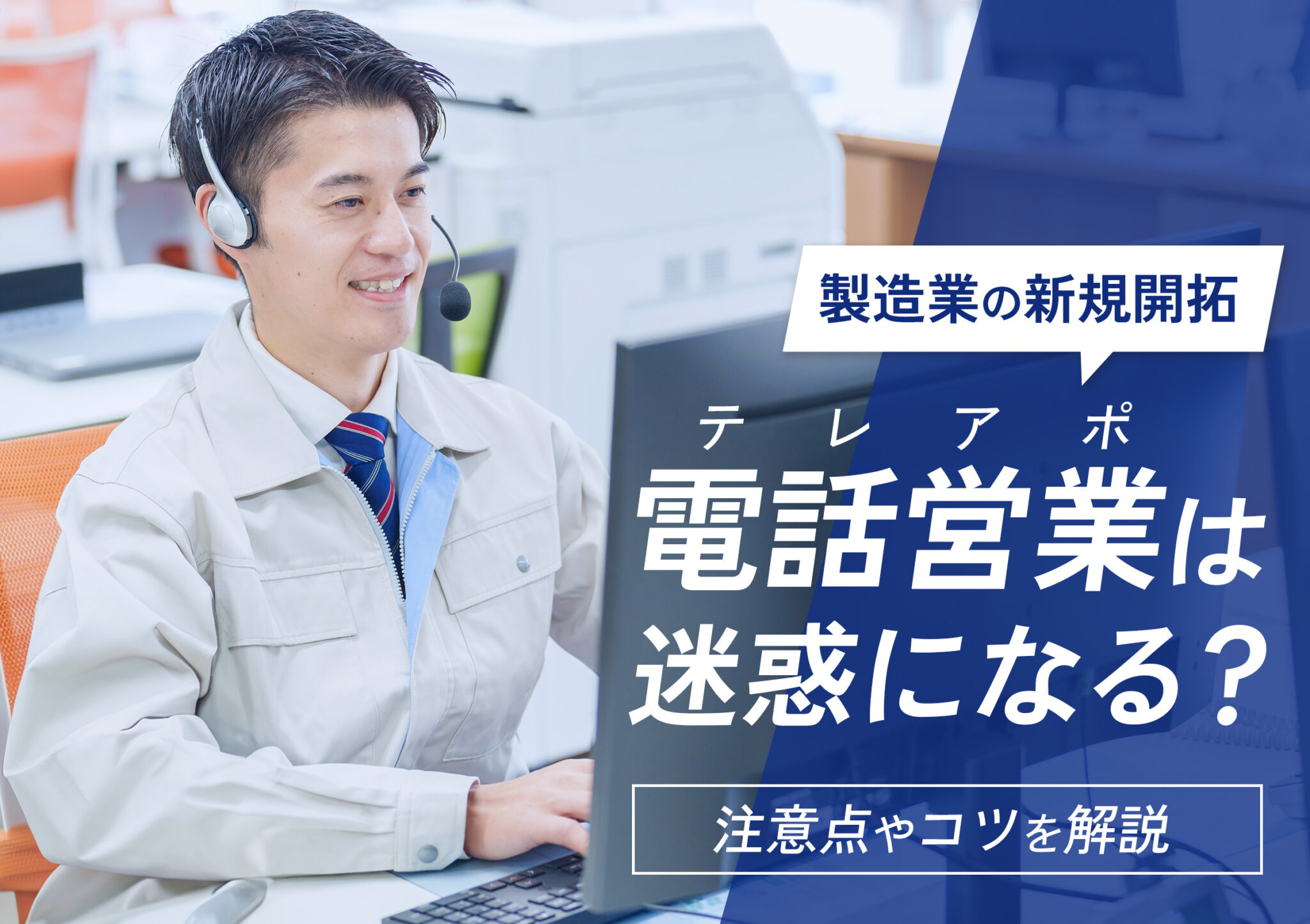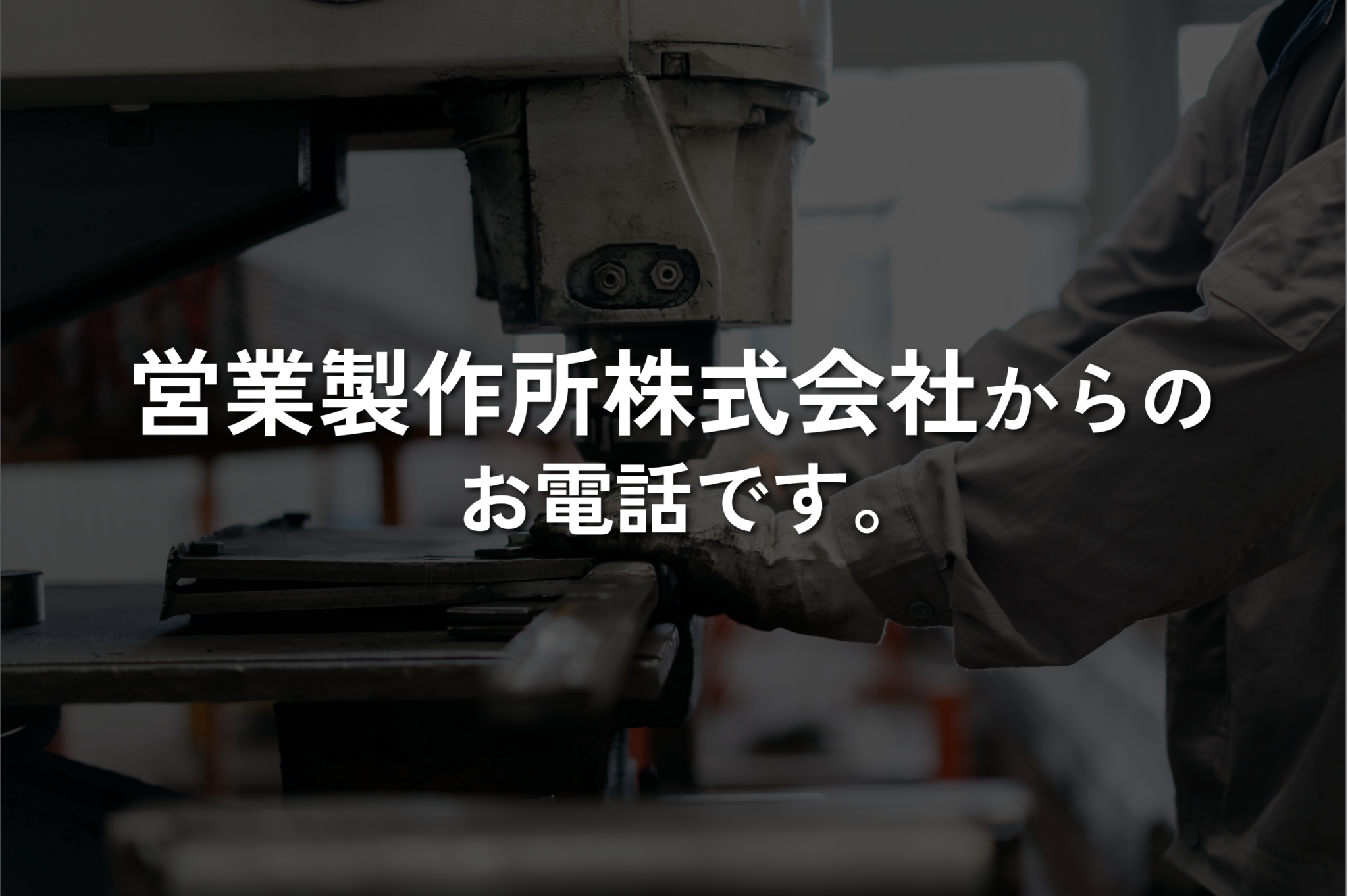展示会は、新規顧客の獲得や見込み客との接点強化に有効な施策のひとつです。展示会への出展により、自社のブランディングなども期待できます。
とはいえ、展示会には十分な準備をして臨まなければ集客に失敗するケースも多く、「展示会で効果的に集客する方法を知りたい」「どうすれば展示会出展を成功させられるのかわからない」といった担当者の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、展示会での集客を成功させるためのポイントやアイデア、注意点などを解説します。そもそも展示会とはどんなものなのか、期待される効果などにも触れるため、はじめての展示会出展を検討している方もぜひ参考にしてみてください。
index
展示会とは?

展示会とは、企業が自社の製品やサービスを実物展示やデモンストレーションを通じて紹介するビジネスイベントです。業界ごとに開催され、参加者は情報収集・商談・比較検討を目的に来場します。出展企業にとっては、新たな顧客との出会いや、自社の魅力を直接伝える貴重な場です。
来場者の多くはすぐに購入・導入を決定するわけではなく、情報収集を主な目的としています。そのため、展示会を通じて接点を持った人々は、すぐに顧客化せずとも中長期的にアプローチする「見込み客」として捉えることが重要です。
近年の傾向として、インターネットの普及により、製品情報やサービスの比較がオンラインで手軽に行えるようになったことで、展示会来場者数自体は減少傾向にあります。このような背景から、限られた来場者の中でいかに質の高いリードを獲得するかが、出展成功のポイントであるといえるでしょう。
製造業向けの展示会出展の営業・運営のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。展示会出展を検討している製造業の担当者の方は、ぜひあわせて参考にしてみてください。
▶︎【製造業向け】展示会出展の営業・運営のポイントは?出展のメリットや費用も徹底解説
展示会出展により期待できる効果
展示会に出展することで期待できる効果やメリットを3つ紹介します。
自社のブランディングができる

展示会では、製品やサービスの紹介にとどまらず、企業の理念やビジョン、業界における立ち位置を来場者に伝えることが可能です。来場者にとって、実際にスタッフと対話したり製品に触れたりすることで、企業に対する理解が深まり信頼感が醸成されます。
また、ブースデザインや配布資料、社員の応対姿勢なども企業イメージに直結するため、これらを通じて自社のブランドを印象づけることが可能です。とくにまだ知名度が高くない企業にとっては、展示会はブランド認知度を高める絶好の場であり、競合他社との差別化にもつながります。
見込み客との接点を作れる

展示会は、製品やサービスに関心を持つ潜在顧客とリアルな場で出会える貴重な機会です。来場者の多くは情報収集を目的としており、購入には至らない場合でも、名刺交換やアンケートの記入、資料請求といったアクションを通じてリード情報を取得できます。
これにより、営業部門がその後のフォロー活動を行いやすくなり、見込み客の育成(リードナーチャリング)にもつながります。展示会を通じた顧客接点の創出は、短期的な成果よりも中長期的な顧客獲得を見据えた施策として重要です。
既存顧客とのコミュニケーションの場として活用できる

展示会は、新規顧客との出会いだけでなく、既存顧客との関係強化の場としても有効です。既存取引先が展示会を訪れた際に、新製品の紹介や新サービスの提案を直接行うことで、継続的な関係を深めたり、アップセルやクロスセルのきっかけを作ったりできます。
展示会での集客を失敗するケース
展示会はただ出展すればいいというわけではなく、適切な準備・対応をしなければ集客に失敗してしまいます。ここでは、展示会での集客を失敗する5つのケースについてチェックしておきましょう。
事前集客が不足している

展示会では、出展するだけで自然と多くの来場者がブースに足を運んでくれるわけではありません。とくに来場者数が限られる近年では、集客を成功させるためには事前の集客活動が重要です。事前告知を行わずに出展当日を迎えると、ブースの存在に気づかれないままスルーされてしまうことも多々あります。
メールやSNS、自社サイトでの告知、招待状の送付、事前アポイントの獲得など、さまざまなチャネルを活用して計画的に集客を進めなければ、費用対効果の高い出展にはなりません。ターゲット層に確実に情報を届け、当日の訪問につなげるための事前準備を行いましょう。
来場者の目的やニーズを理解できていない

展示会に訪れる来場者には、それぞれ異なる課題や目的があります。それらを理解せず、画一的な説明や売り込みをしてしまうと、相手の関心を引けずにブースから離れてしまう可能性があります。
来場者の多くは情報収集フェーズにあり、すぐに購入や商談に移るわけではありません。そのため、製品のスペックを一方的に伝えるのではなく、相手の業種・職種・業務上の課題をヒアリングし、それに応じた提案を行うことが求められます。事前に想定されるペルソナを設定し、訴求ポイントを整理しておくことが効果的なアプローチにつながるでしょう。
効果的なブース設計ができていない
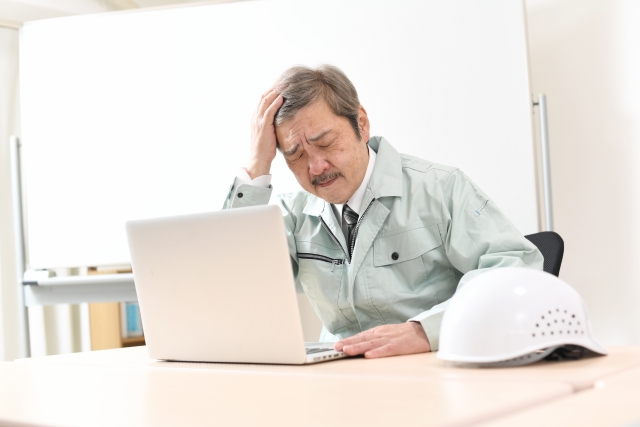
展示会では、限られたスペース内でいかに自社の魅力を伝えるかが重要です。しかし、ブースの設計が雑然としていたり、コンセプトが不明瞭であったりすると、来場者の目に留まらず通り過ぎられてしまうことがあります。装飾や掲示物が多すぎて情報過多になっているケースや、逆にブースが寂しすぎて目立たないケースも失敗の一因です。
また、動線設計が悪く、立ち寄りにくいブースになっていると集客効果はさらに下がります。来場者の目線に立ったレイアウト・視覚的な訴求力のあるビジュアル・わかりやすいメッセージなど、戦略的なブース設計が必要不可欠です。
ブースの雰囲気や対応がよくない

来場者は、ブースの雰囲気やスタッフの対応を通じて、その企業の姿勢や文化を無意識に評価しています。「笑顔や挨拶がない」「質問に的確に答えられない」「案内が不十分」といった接客の質の低さは、来場者の興味を失わせる要因になるため要注意です。
また、無表情で立っているだけのスタッフや、来場者に話しかけずに内輪で雑談している様子が見られると、ネガティブな印象を与えかねません。展示会においては、限られた時間で最大限の印象を残すことが大切です。スタッフ教育やロールプレイを事前に実施し、訪問者に好印象を与えられる対応を徹底しましょう。
ブース訪問者へのフォローが不足している

展示会終了後のフォロー体制が不十分だと、せっかく得た見込み顧客を失う結果になりかねません。名刺交換や資料請求を通じて得た情報をそのまま放置してしまうと、相手の関心が薄れてしまい、商談機会を逃すことになります。
展示会はリード獲得の場であり、その後のアクションが成果を大きく左右します。訪問者ごとの関心度や温度感に応じたメール配信・電話フォロー・セミナー案内などをタイムリーに実施することが重要です。また、CRMなどのツールを活用して情報を一元管理し、営業チームと連携しながら次のアクションに繋げる体制を整えましょう。
展示会で集客を増やすための4つの事前準備
展示会で集客を増やすために重要な4つの事前準備について解説します。
展示会出展の目的を明確化する

展示会に出展する際は、単なる出展ではなく「何のために出展するのか」を明確にすることが重要です。たとえば、新規顧客の獲得を目的とするのか、既存顧客との関係強化を図るのか、ブランド認知の向上を目指すのかで、取るべき施策が変わってきます。
目的が不明確なままでは、展示内容やブース設計、スタッフの対応方針に一貫性がなくなり、結果として来場者への訴求力が弱くなるおそれがあります。限られた時間・予算の中で最大限の成果を出すためにも、出展の目的は事前にチーム全体で共有し、KPI(重要指標)と紐づけておくことが大切です。
ターゲット像を明確化する

効果的な展示会集客には、明確なターゲット設定が不可欠です。製品やサービスを誰に届けたいのか、どの業界・どの職種・どの規模の企業が対象なのかを詳細に設定することで、訴求メッセージやブース設計が最適化されます。
また、ターゲットによって集客チャネルやコミュニケーション手段も変わる点には注意が必要です。事前のペルソナ設計や過去の来場者分析を活用し、自社の提供価値が最も響く相手にリーチできるよう、設計段階から意識しておきましょう。
事前集客に注力する
当日になってはじめて認知されるのでは遅く、展示会の集客は事前からの仕込みが重要です。興味を持ってくれそうな顧客に事前にアプローチしておくことで、来場者数と質の両方を高められます。主な事前集客の手法は以下のとおりです。
- メールでの事前集客
- 電話での事前集客
- SNSでの事前集客
- プレスリリースでの事前集客
- ウェビナー・オンラインイベントからの事前集客
それぞれの手法について解説します。
メールでの事前集客

既存顧客やメルマガ登録者、過去の展示会来場者などのリストを活用し、展示会出展の案内メールを配信します。展示内容や見どころ、特典などを記載し、来場メリットを明確に伝えることがポイントです。
メールでの事前集客にも活かせるメール営業のコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
▶︎製造業の新規開拓|メール営業とは?書き方を例文付きで解説
電話での事前集客

重要な見込み顧客に対しては、電話での事前案内も有効です。とくにBtoB商材の場合、決裁者層との関係構築が重要になるため、パーソナルな連絡による来場促進が効果を発揮します。電話での事前集客も含む電話営業(テレアポ)のポイントについては、以下の記事もチェックしてみてください。
▶︎製造業の新規開拓|電話営業(テレアポ)は迷惑になる?注意点やコツを解説
SNSでの事前集客

企業の公式SNSアカウントを通じて展示会の告知を行うことで、フォロワーやその周囲へリーチが広がります。ハッシュタグの活用や、展示ブースの写真・動画を使った投稿も注目を集めるために役立つでしょう。
プレスリリースでの事前集客

メディア向けに展示会出展情報を発信することで、業界紙やWebメディアに取り上げられる可能性があります。広範囲に向けた認知拡大を図る手段として有効です。
ウェビナー・オンラインイベントからの事前集客

展示会前にオンラインセミナーや説明会を開催することで、見込み顧客との接点を先に持ち、当日の来場につなげることができます。関心層との接触を段階的に深める手法として有効です。
製造業向けのWebセミナー開催の手順については、以下の記事で解説しています。はじめてのウェビナー開催を検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。
▶︎【製造業向け】はじめてのWebセミナー開催|手順や注意点も解説
ブースの設計にこだわる

ブースは展示会における店舗のような存在です。遠くからでも目に留まりやすいデザイン、導線を意識したレイアウト、そして滞在時間を長くするための設計が求められます。展示物の見せ方やスタッフの配置も含め、目的とターゲットに合ったブースを設計することが集客成功のポイントになるでしょう。
また、受付からの導線がスムーズであることや、出入口の位置、案内表示の分かりやすさなど、来場者視点に立った細やかな配慮が重要です。近年では、体験型のコンテンツやデジタルサイネージを取り入れるなど、滞在時間を延ばすための工夫も注目されています。
展示会で集客を増やすための当日対応
展示会での集客を増やすための当日対応として、やるべきことや効果が期待できるアイデアを7つ紹介します。自社での出展計画に役立ててみてください。
スタッフ配置を最適化して声かけと接客を行う

展示会当日は、限られた時間の中でいかに多くの見込み客と接点を持てるかが重要です。そのためには、ブース内でのスタッフの配置を最適化し、動線を意識した役割分担が不可欠です。たとえば、以下のような役割分担を事前に決めておくと、スムーズに対応できます。
- 来場者への初期対応を行う人
- 詳しい説明やデモンストレーションを担当する人
- 資料配布や名刺交換を行う人
また、来場者が近づいてきた際にタイミングよく声をかける「呼び込み担当」を配置することで、集客効果が高まります。事前に動線や会話パターンをシミュレーションしておくと、現場での混乱も防げるでしょう。
接客の流れを打ち合わせておく

展示会では多くのスタッフが関わるため、接客の質を均一に保つためにも、対応の流れを事前にしっかりと打ち合わせておく必要があります。たとえば「名刺交換→ヒアリング→サービス説明→資料提供→次のアクション確認」といった一連の流れを共有し、全員がその手順で対応できるようにしておくと、ブース全体に統一感が生まれ、来場者にも好印象を与えられるでしょう。
また、顧客の興味・関心を把握するための質問項目や、製品の訴求ポイントも整理しておくと、誰が対応しても一定レベルの案内が可能になります。名刺の渡し方や資料の渡し方など、細かな動作も含めてロールプレイしておきましょう。
顧客のニーズや目的に合うコンテンツを展示する

展示会に訪れる来場者は、明確な課題や目的を持っている場合が多いため、ニーズにマッチしたコンテンツを展示することが集客成功のためのポイントとなります。単に製品やサービスを陳列するだけでなく、「誰に向けて」「どんな課題を解決できるか」を明確に伝える工夫が必要です。
たとえば、業界別の事例紹介パネルや、用途に応じた製品の使い方を示す資料、QRコードからアクセスできる導入事例動画などを活用することで、来場者の関心を引きやすくなります。また、実際のユーザーの声や比較データを提示すれば、信頼感も高まりやすいでしょう。
集客につながる配布物を活用する

配布物は、展示会後も自社を思い出してもらうための重要なツールです。一般的なパンフレットやチラシに加え、機能的なノベルティや来場者の業務に役立つ資料など、持ち帰りたくなる工夫を凝らすことで、記憶に残る接点を作れます。たとえば、業界データをまとめた小冊子やチェックリスト、ダウンロード特典の案内など、来場者の課題解決につながる実用性のある内容が好まれます。
名刺交換と引き換えに特典を提供する形式にすれば、確実にリード情報を取得することも可能です。なお、配布物には企業名・製品名・連絡先を明記しておくと、後日の問い合わせや資料請求にもつながります。
デモンストレーションなどの体験型コンテンツを活用する

ブース内で実際に製品やサービスを体験してもらえるデモンストレーションは、来場者の関心を引きつけ、印象に残すうえで非常に効果的です。たとえば、製品の操作性や性能をその場で確認できる実演や、タッチパネルやモニターを用いたインタラクティブな紹介などは、受け身の説明よりも強く訴求できます。
デモに参加することで、来場者は自分ごととして商材を理解しやすくなり、その場での質問や会話も自然と生まれます。また、デモスケジュールを事前告知しておけば、時間を合わせてブースを訪れる来場者も増え、集客効果をさらに高められるでしょう。記録用にデモの様子を撮影し、後日SNSやWebに活用するのも有効です。
展示会の様子を配信する

当日の様子をリアルタイムで配信することで、会場に来られない潜在顧客にもアプローチが可能です。ライブ配信やSNS投稿を活用すれば、展示会に参加していないフォロワー層にも自社の取り組みを知ってもらえるうえ、後日動画として再利用もできます。
たとえば、ブースの雰囲気・製品紹介の様子・担当者インタビューなどを動画化し、YouTubeやInstagram、LinkedInなどで発信することで、ブランディング効果や認知拡大が期待できます。また、配信コンテンツに視聴者のコメント機能を設けることで、非対面ながらも双方向のコミュニケーションを図ることも可能です。リアルとオンラインの両軸で情報発信を行いましょう。
KPIを設定して改善しながら進める

展示会の場では、来場者の数や名刺交換の枚数といった表面的な数字だけでなく、最終的な商談・受注につながる動きがどの程度あったかという点まで含めて成果を測定する必要があります。KPI(重要業績評価指標)を事前に設定しておくことで、効果検証がしやすくなり、現場での改善にもスムーズに活かせるでしょう。KPIの例は以下のとおりです。
- 1日あたりの名刺獲得数
- デモ参加者数
- 商談化率
- 資料請求の数
上記のような項目を目標数値として明示し、会期中にも進捗を確認しましょう。これにより、声かけの強化や配布資料の内容変更など、柔軟な調整も可能になります。
展示会出展時の注意点
展示会出展時の主な注意点を4つ紹介します。
過度な声かけや派手なブースデザインは逆効果

展示会では来場者にアプローチする姿勢が重要ですが、過度な声かけや、過剰に目立つブース装飾は逆効果になるおそれがあります。声をかけられすぎると来場者は圧迫感を感じ、ゆっくりブースを見られなかったり、そもそも立ち寄るのを避けられたりするケースもあるため要注意です。
とくにBtoBの展示会では、来場者は情報収集や比較検討が目的であることが多く、押し売りのような印象を与えると印象を悪くしてしまいます。また、ブースデザインが派手すぎると、企業イメージや商材とのギャップを生みかねません。視認性や導線の確保は大切ですが、あくまでブランドイメージやターゲット層に合った立ち振る舞いを意識することが重要です。
名刺を切らさないように注意

展示会では名刺交換が最も基本的な顧客接点のひとつとなります。想定よりも来場者数が多かった場合や、スタッフの名刺準備が不十分だった場合、名刺が切れてしまうと大きな機会損失に繋がります。
名刺がないことで連絡先の共有や後日のフォローが難しくなり、せっかくの商談チャンスを逃してしまう可能性もあるため、会期中に余裕を持って名刺を持ち込んでおくことが大切です。万が一名刺が切れてしまった場合に備えて、デジタル名刺の準備や、連絡先を記入してもらえるフォームなども用意しておくと安心です。
その場で商談が始まっても対応できる体制で望む

展示会では、製品やサービスに強い関心を持つ来場者が現れた場合、ブース上でそのまま商談が始まることもあります。そのため、製品に関する詳しい知識を持ったスタッフや、価格・納期・導入方法などについて具体的に話ができる担当者を最低1名は常駐させておくべきです。技術的な質問や見積もりの依頼に即時対応できない場合、せっかくの商談機会を逃してしまう可能性があります。
また、商談が始まった場合の導線やスペースもあらかじめ確保しておくと、落ち着いて対話ができ、他の来場者への対応にも支障が出にくくなります。事前に社内で役割分担や対応フローを打ち合わせておきましょう。
展示会後のフォローを忘れずに行う

展示会で得た名刺やリード情報は、その後の営業活動につなげていくための貴重な資産です。展示会の成果は、その後にどれだけ商談や契約に結びついたかで評価されるため、展示会終了後のフォローが重要だといえます。
展示会終了から時間が経つほど、来場者の熱量や記憶は薄れていくため、遅くとも1週間以内にはメールや電話などでお礼と情報提供のフォローを行うのが理想です。また、リードの関心度やニーズに応じてアプローチ方法を変える、セミナーや資料の案内を送るなどの工夫も有効です。
展示会の効果の測定方法
展示会に出展したことによる効果の測定方法について解説します。
費用対効果を測定する

展示会の成果を正しく評価するためには、まず費用対効果(ROI)を測定することが不可欠です。具体的には、展示にかかった総コスト(ブース出展費、設営費、パンフレット制作費、スタッフの交通・宿泊費、人件費など)に対し、展示会によって得られた売上・受注や今後の商談につながるリードに紐づく予測収益などを合わせて比較します。
具体的な計算式は以下のとおりです。
費用対効果(ROI)={(出展による利益・効果)ー(出展にかかった総費用)}÷(出展にかかった総費用)
BtoBのように販売まで時間がかかるケースでは、リード数や商談化率などを成果指標として代替することも有効です。
複数の展示会に出展して成果を比べる

もし複数の展示会に出展している場合、それぞれの成果を共通の基準で比較することで、費用対効果の高い展示機会を把握できます。たとえば、出展費1万円あたりどれだけのリードや商談が得られたか、ROIが高かったかなどの指標比較が有効です。
また同じ目的で出展している展示会間で成果を比較することで、ターゲット層や地域、会期、出展方法などの違いがどう影響するのか把握でき、今後の出展戦略に活かせます。こうした比較分析を通じて、次回以降に向けた出展のPDCAサイクルを回していくことが重要です。
展示会での集客の成功事例
展示会での集客の成功事例を2つ紹介します。
事例①:中小IT企業の問い合わせ倍増の成功例
中小IT企業A社では、新製品の認知拡大と見込み客獲得を目的に展示会に出展しました。出展前に業界向けウェビナーに参加したリストに案内メールを配布し、SNSでも定期的に出店予告を行うなど、事前集客も徹底しました。その結果、来場者数が前年比で30%増加を達成しています。
さらに、名刺交換したリードのうち、50%がフォローアップ後の問い合わせにつながり、7件の商談を獲得しました。最終的に2件が成約に結びつき、出展費用の2.5倍の売上を達成した成功事例です。
事例②:製造業のリブランディング成功例
製造業B社は、地方の見本市に出展することでブランド認知の向上を目指しました。展示会では業界特有の課題解決事例や新技術のデモを配置し、顧客ごとのニーズに合わせた提案を行いました。その結果、新たに20社の見込み客と名刺交換、8件の商談アポイントを獲得しています。
そのうち、3件が成約し、展示会のブランド認知効果を図るアンケートでも「知らなかったが出展で知った」と答えた来場者が全体の40%に達しました。これを受け、展示会以降は知名度アップの施策が強化され、展示会の目的達成にもつながった成功事例です。
2025年開催の主な展示会
2025年開催の主な展示会を3つ紹介します。
製造業向けの展示会については以下の記事でよりたくさん確認できます。
▶︎ 【2025年版】製造業向け展示会29選|エリア別まとめ
中小企業 新ものづくり・新サービス展

「中小企業 新ものづくり・新サービス展」は、日本のものづくりを支える中小企業の技術や新サービスを広く紹介し、バイヤーや事業パートナーとのマッチングを促進する総合商談展示会です。業界を超えて多彩な業種が出展できる「オールジャンル型」の展示会であり、オンライン出展など柔軟な出展フォーマットを活用できます。
| 会期 | 2025年12月16日〜12月18日 |
| 会場 | 東京ビッグサイト東7・8ホール |
| 出展費用 | ブース出展:30,000円 オンライン出展:無料 |
| 出展申込締切 | ブース出展:2025年8月29日 オンライン出展:2025年10月31日 |
中小企業 新ものづくり・新サービス展の詳しい情報はこちら
Japan IT Week, Japan DX Week【関西】

Japan IT Week Osakaは、関西最大規模のIT/デジタル・トランスフォーメーション(DX)展示会です。11月にインテックス大阪で開催され、250社の出展と約12,000名の来場者が見込まれています。展示ジャンルは幅広く、ITの基盤から最新動向までを網羅する構成となっています。
| 会期 | 2025年11月19日〜11月21日 |
| 会場 | インデックス大阪1〜3号館 |
| 出展費用 | 要問い合わせ |
| 出展申込締切 | 要問い合わせ |
Japan IT Week, Japan DX Week【関西】の詳しい情報はこちら
ものづくりワールド

ものづくりワールドは、製造業の設計・開発・生産技術・DX・IoT・物流・部品調達までを網羅する、日本最大級の製造業向け専門展示会です。東京・大阪・名古屋・福岡で毎年開催されており、業種・職種に特化した10以上の専門展で構成されています。
| 会期 | 大阪:2025年10月1日〜10月3日 福岡:2025年12月3日〜12月5日 名古屋:2026年4月8日〜4月10日 東京:2026年7月1日〜7月3日 |
| 会場 | 大阪:インデックス大阪 福岡:マリンメッセ福岡 名古屋:ポートメッセなごや 東京:東京ビッグサイト |
| 出展費用 | 要問い合わせ |
| 出展申込締切 | 要問い合わせ |
ものづくりワールドの詳しい情報はこちら
展示会以外に顧客と接点を持つ方法
見込み客と接点を持つ方法は、展示会以外にもたくさんあります。ここでは、自社に興味を抱いている見込み客との接点を強化し、商談・成約に繋げるための方法を3つ紹介します。
なお、ここで紹介する以外の新規顧客獲得施策や販路拡大施策については、以下の記事をチェックしてみてください。
▶︎新規顧客を増やすには?集客方法やリード獲得手法を解説
▶︎販路拡大とは?メリットや基本戦術、具体的な方法を解説
ウェビナーを開催する

ウェビナー(Webセミナー)は、場所を問わず多くの見込み客にアプローチできる手段として注目されています。とくに製品説明や業界の最新トレンド解説など、専門性の高い情報を提供できれば、課題感を持つ見込み客に強く刺さりやすいのが特徴です。
リアルタイムで質問対応ができるライブ配信形式や、いつでも視聴可能なオンデマンド形式など、内容に応じて配信方法を選択できます。また、申込時に得られる氏名・メールアドレスといった情報を活用し、終了後のフォローアップや営業活動に繋げやすいという点でも有効です。
イベントやセミナーを開催する

小規模なリアルイベントや自社主催のセミナーも、顧客と直接接点を持つ有効な手段です。特定の業種やテーマに絞ったセミナーを開催すれば、関心度の高いリードが集まりやすく、密度の高いコミュニケーションを実現できます。
たとえば、導入事例紹介や課題解決型セッションなどを組み合わせることで、自社の信頼性を高めるだけでなく、参加者の購買意欲を喚起することもできます。さらに、セミナー後のアンケートや個別相談会を設けることで、参加者との関係性をより深め、商談への移行率を高める施策にもつながるでしょう。
クーポン配布や無料トライアルを実施する

とくに新規顧客や検討段階の見込み客に対しては、クーポン配布や無料トライアルの提供が有効です。資料だけでは理解が難しい製品やサービスでも、実際に体験してもらうことでメリットを直感的に理解してもらえます。
たとえば、SaaS製品であれば「14日間無料」などの期間限定トライアル、ECサイトであれば初回限定の割引クーポンなどが代表的です。これらの特典は、ウェブ広告やメールマーケティング、SNSを通じて広く訴求できるため、展示会ではリーチしきれない層にもアプローチできます。トライアル後に自動でフォローアップメールを配信するなど、システム連携による営業活動の自動化も効果的です。
展示会での集客に関するよくある質問
展示会での集客に関するよくある質問とその回答を紹介します。
展示会でやってはいけないことは?

展示会では、派手な演出は逆効果です。たとえば、過度な呼び込みや押しつけがましいトークは、来場者の興味をそぐ原因になります。また、スタッフの対応が雑だったり、訪問者への対応がマニュアル化されていないと、せっかくの集客チャンスを逃すことになるでしょう。
さらに、名刺やパンフレットを切らしてしまうとリード管理にも支障が出ます。展示会の効果を最大限に引き出すには、来場者にとって心地よい対応・雰囲気づくりを意識し、過度な演出や自己中心的なアプローチを避けることが重要です。
展示会での集客に役立つツールは?
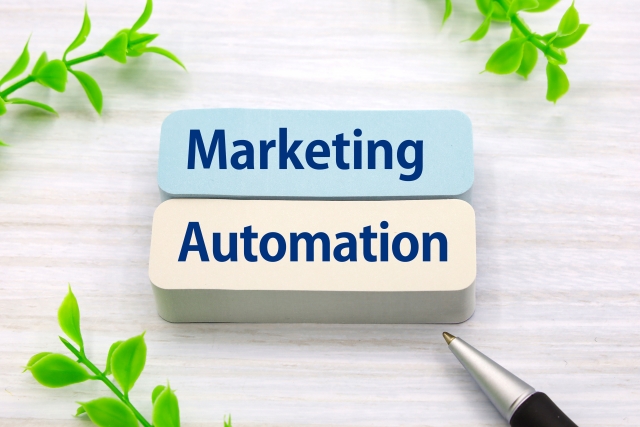
展示会でのリード獲得やフォローアップには、MA(マーケティングオートメーション)ツールの活用が効果的です。MAツールは、展示会前の事前アプローチ(メール配信やセグメント管理)や、展示会後のフォローメール、スコアリングによる見込み客の選別に活用できます。
来場者の反応をもとに、商談につながりやすい顧客を優先的にアプローチできるため、営業効率の向上にもつながるでしょう。展示会を単発のイベントで終わらせず、その後のマーケティング活動へつなげるうえでも、MAツールは強力なツールです。
展示会での集客をサポートしてくれるサービスはある?

自社だけで展示会を準備・運営するのが難しい場合、展示会支援サービスの活用も検討しましょう。たとえば、ブース設計から当日の運営スタッフの手配、事前集客、展示会後のリード管理までをトータルで支援してくれる企業もあります。
こうしたサービスは、展示会出展の経験が浅い企業や、社内リソースが限られている場合に有効です。専門の知見を持つプロに任せることで、より戦略的で効率的な展示会運営が実現できます。目的や課題に応じた支援内容を選ぶことで、自社の強みを活かした集客活動が可能となるでしょう。
展示会の事前集客や営業活動に充てる人材が不足しているときは?

社内に営業人材が足りず、展示会の事前準備や当日の対応が不安な場合は、営業代行サービスの活用が有効です。営業代行を利用すれば、事前のリスト作成やテレアポ、メール配信といった集客活動を外部に委託できるため、自社の人的リソースを他の業務に集中できます。
また、営業のプロが代行することで、リード獲得の質も高まりやすくなるでしょう。営業代行会社の中には展示会に特化したノウハウを持つところもあるため、展示会と営業代行の連携によって、より高い成果が期待できます。
製造業向けの営業代行については、以下の記事で詳しく解説しています。営業リソース不足で悩んでいる製造業の担当者の方は、ぜひチェックしてみてください。
▶︎製造業におすすめの営業代行20選!選び方や注意点も解説
新規顧客獲得なら営業製作所がおすすめ
Eigyo Engineは、製造業に特化した180万社のデータベースを基に、加工方法や材質など技術を必要としている企業を絞り込み、専任リサーチャーが厳選した「強みを活かせる案件」をご紹介する営業代行・マッチングサービスです。
「技術的な強みを活かせる案件が少ない」
「営業代行に依頼しても、アポイントの質が低い」
「新規開拓をしたいが、どのようにアプローチすればよいかわからない」
こうしたお悩みを、Eigyo Engineがすべて解決します。
60万件以上のリサーチタグを活用し、業界・エリア・ロットはもちろん、加工方法や材質といった「技術ニーズ」、外注状況や設備投資状況などの「発注ニーズ」まで、より高精度な絞り込みを可能とします。 さらに、製造業に精通した専任リサーチャーが、候補企業に直接電話でヒアリングを行い、「発注したい仕事内容」を把握。お客様の技術的な強みに最もマッチする案件だけを厳選してご紹介します。